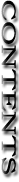栽培、海外ラン園視察などに関する月々の出来事を掲載します。内容は随時校正することがあるため毎回の更新を願います。 2023年度
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
12月
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
| Vanda luzonica Luzon | Vanda merrillii Luzon | Vanda dearei Borneo |
 |
 |
 |
| Dendrobium datinconnieae Borneo | Dendrobium jyrdii Palawan | Dendrobium intricatum Thailand |
 |
 |
 |
| Bulbophyllum fritillariflorum PNG | Bulbophyllum sp aff. fritillariflorum PNG | Bulbophyllum grandiflorum Sumatra |
 |
 |
 |
| Bulbophyllum fraudulentum PNG | Bulbophyllum laxiflorum Mindanao | Bulbophyllum magnum Luzon |
Bulbophyllum makoyanumの杉板への植替え
現在マーケットではほとんど見られない稀少性の高いバルボフィラムやデンドロビウムの植替えを優先的に行っています。今回取り上げるのは、バルボフィラム趣味家には良く知られたBulb. makoyanumで、本種はマレー半島、ボルネオ島、フィリピン、ベトナムなどの標高300m以下の低地に生息し、マーケットにて入手は容易で、価格も手ごろなランです。しかし生息域が広範囲であることは見方を変えれば、その中にはこれまでにない個体差をもつフォームや変種が存在する可能性も高くなります。下画像はそうしたマーケットではほとんど見られない2種を選び、先週植替えを行いました。下画像左はフィリピンレイテ島生息種で、本種が一般種と異なる点はラテラルセパル(以下LS)の長さです。J. Cootes氏の著書Philippine Native Orchid SpeciesによるとBulb. makoyanumのLSは4㎝(IOSPEは3.75㎝)とされており、放射状に展開した花全体の直径(横幅)は9㎝前後となります。一方、下画像種は1輪のLSの長さが最長6.5㎝ほどで、横幅はメジャーが示すように14㎝です。このサイズは毎回の開花に継承されています。現在30株以上のボルネオ島、ベトナム、フィリピン生息の本種を栽培していますが、この幅サイズを超える株は他には見られません。画像右はパラワン生息種で、一般種のLSは黄色系のべース色に赤い斑紋が不規則に点在しているものの、本種はこうした斑紋が極薄で、ほぼ黄系一色です。またLSの幅はレイテ島生息種の2㎜に対し3㎜とやや太く、レイテ島maloyanumとその類似種であるBulb. brevibrachiatumとの中間的形態となっています。この2種の類似関係については本ページ1月に記載しています。ちなみにパラワンにはBulb. brevivrachatumの生息は現在確認されていません。パラワンからのラン属の入荷は難しいこともあり、果たしてこのフォームを現在入手可能かどうかは分かりません。
下画像左はレイテ生息種を60㎝長の杉板に、また右のパラワン種は40㎝長の杉板に、それまでの炭化コルクから植替えたものです。当サイトでは8月から現在までに植替えを行ったバルボフィラムの支持材は全て杉板としています。
 |
 |
| Bulbophyllum makoyanum Leyte | Bulbophyllum makoyanum Palawan |
現在(21日)開花中のデンドロビウム6種
Den. bandiiはDie Orchidee Journal 2020年2月に発表された直近の新種で、スマトラ島北部標高1,300m-1,600mの生息種とされます。当サイトがマレーシア経由で本種を得たのは、sp(種名不詳種)として2016年12月で、上記発表の4年前となります。初花は2017年3月の当ページに掲載しました。Journal記載の標高値からは中温タイプとなりますが、当サイトではこれまで通年で高温室にて栽培をしてきました。今回の下画像も高温室での撮影です。しかし3か月間に及ぶ今年の猛暑時には成長の鈍化が観察されたことから、来年の夏期は中温室に移動となります。現在は開花と共に新芽が伸長していることから、来春に炭化コルクから木製バスケットに植替える予定です。Den. modestumについては、大型バスケットに5年間複数株を一纏めにした寄せ植えから、先月1株づつに分けて木製バスケットに植替えたことを報告しました。この影響か、下画像に見られるような多輪花での開花が始まりました。またDen. mutabileも長い期間それまでの小さなプラスチックポットの植え付けから8月にバスケットへ植替えたことで、まるで目覚めたかのように開花が続いています。いずれの種も根の窮屈な環境は嫌なようです。
 |
 |
 |
| Dendrobium bandii Ache Sumatra | Den. cinnabarinum v. angustitepalum Borneo | Dendrobium modestum Polilio Philippines |
 |
 |
 |
| Dendrobium mutabile Sumatra | Den. sp aff.2 punbatuense Borneo | Dendrobium victoriae-reginae Luzon |
現在(20日)開花中のDracula felixとBulbophyllum ankylochele
現在、Dracula felixと、4-5日後には全開となるBulb. ankylocheleが開花しています。これらにはいずれも通年で夜間平均温度を10℃-18℃範囲内とする温度管理が必要で、国内の今年の様な猛暑となる夏期にはエアコン等による空冷設備が無くして栽培は出来ません。それが無理であれば、1年程は葉先が枯れてじり貧状態にはなるものの、なんとか持ち堪えますが、生きた根が無くなりやがて枯れ果てます。凡そ販売する業者の言葉ではないと感じられる方が多いと思いますが、今後も続くと言われる夏季の猛暑下で、低―中温系のランをこれから栽培しようとする趣味家へのアドバイスと思って下さい。それほど多くの方々からこうしたcold(10 - 15℃)からcool(15 - 18℃)系の属種の栽培失敗談をよく耳にします。その殆どの原因は、栽培技術と云うよりは、それ以前の当該種の栽培環境の必要最小条件を満たしていないことに尽きます。下画像左は1株に咲いているDraculaの花で、画像枠外の10輪ほどの花も含めると30輪以上の同時開花となります。目も鼻もある人や猿の様な顔だちならぬ花だちを見ると、栽培したくなる人も多いと思いますが、それにはそれなりの栽培経費を覚悟しなければなりません。当サイトで栽培しているDraculaは現在60種程あり、常に数種類の花を通年で見ることができます。
 |
 |
| Dracula felix Ecuador | Bulbophyllum ankylochele New Guinea |
Blubphyllum vinaceum
本種はボルネオ島標高400m - 1,000mに生息するバルボフィラムで、当サイトがバルボフィラムの収集を始めた10年以上前の入手株の一つです。今回本種を取り上げるのは、ネット情報に不明な点があるためです。まず本種はシノニム(異名同種)として、タイ、マレー半島及びスマトラ島に生息のBulb. elevatopunctatumが知られています。しかしこの種についてはCoolからWarmとの栽培温度に関する記載はあるものの、具体的な生息標高データはどのネット上のサイトにもありません。Bulb. vinaceumとelevatopunctatumはシノニムの関係であっても別名である限り、地域差や生息標高差による形態の違いが僅かでもある筈で、その違いを視覚的に確認したいのですが今のところ両者は混在して取り扱われており確証的な違いや定義が見つかりません。サイトの中にはBulb. elevatopunctatumの生息域にボルネオ島を含める記載もあるほどです。一方、IOSPEでは花サイズに関しBulb. vinaceumは2cm、Bulb.elevatopunctatumは3㎝としています。しかし当サイトのBulb. vinaceumの花サイズは現在開花中の花が5.5㎝で、2倍以上の違いがあります。花サイズの違いは雲霧林帯の生息種に見られるように午前・午後の開花様態が異なることもあり、花サイズを定めることが難しいことは理解できますが、Bulb. vinaceumは昼夜で開花様態が変化する種ではありません。よって2.5倍の差となれば、当サイトの株は、とんでもない変異種になってしまいます。当サイトでの過去の本種の花サイズの最小値は4㎝です。 こうした花サイズの大きな違いは、これまで別種でも再三観測し、その都度本ページにて報告しています。下画像は本種の炭化コルクから杉板への植替え前と後の様子となります。一般的に開花や小さな新芽の伸長中に植替えを行うのは好ましくありませんが、植替え順番待ちの時間的制約故の強行実施です。画像下の青色種名のクリックで本種の花サイズやリップ等の詳細画像が見られます。
 |
 |
 |
| Bulbophyllum vinaceum Borneo 植替え前の炭化コルク付け(中央) | 杉板60㎝への植替え | |
Blubphyllum sp aff. ocellatumの杉板への植替え
2015年12月にBulb. pardalotumとしてフィリピンから入荷した本種は、下画像左に見られるようにセパル・ペタルの基部に赤茶色の線状斑紋を僅かに残しているものの花被片の殆どは金色に覆われており、Bulb. pardalotumとは異なるフォームでした。明るい金色が良く目立つ種でありながら、このフォームと一致する種は国内外共に見られません。このため2021年頃まではBulb. pardalotumの変種と見做し、yellowの付帯名を付けてきました。しかしセパル・ペタル形状がBulb. pardalotumはやや細身に対して本種は丸みがあること、またリップ側弁形状はBulb. ocellatumにむしろ類似することが分かり、さらに入荷ロット全株が同一フォームで、且つこのフォームは一過性でなく、入荷時から変わらず継承・維持されていることから、本種はBulb. pardalotumやocellatumとは類似種ではあるものの、独立した種で稀少性も高いと判断し、現在はBulb. ocellatum aff.としています。これら類似種との相違点の詳細は本歳月記2021年7月やBulb. pardalotumやocellatumそれぞれのページ内にも取り上げています。入荷時から今にちまで本種の植替えは一度のみで、杉皮から炭化コルクへの植替えでした。5-6年間で株は下画像中央に見られるように、多くのバルブが支持材を覆い、これらのバルブや根は数年空中に浮いたままの状態となっていました。にも拘らず成長が続いてきたのは、温室内では通年で80%以上の夜間相対湿度が維持されているためです。しかし気根植物の多くは、活着できないバルブ根が増えるほど株サイズに相応した開花数は得られません。
そうした背景と本種のフォームは前記類似種と比べ観賞性が高いことを考え、今回植替えを行うことにしました。右画像は1m(60㎝と40㎝を接続)の杉板1枚当たりに中央画像の葉付きバルブ数30個以上をそれぞれ植え付けた様子です。奥3列目の60㎝長杉板は、植替えの際に出た切り端のバルブで、通常ならば廃棄するものですが生きた根が多くあったバルブを選び、新芽の発生を期待し寄せ植えしたものです。
 |
 |
 |
| Bulbophyllum sp aff. ocellatum 植替え前の炭化コルク栽培(中央) | 杉板1mへの植替え | |
現在、上画像中央と同じ様なバルブ数がさらに2組あり、これらも順次植替えを予定しています。 下画像は類似種間での比較です。
 |
Bulbophyllum weberi
現在フィリピン固有種のBulb. weberiが開花しています。当サイトでの本種はミンダナオ島低地生息の高温タイプで、二つの花フォームを栽培しています。一つは下画像左のラテラル・セパルがクリームイエローをベース色に赤茶色の斑点に覆われた一般フォームと、他は下画像中央の薄緑のベース色にその基部に僅かな斑点のあるグリーンフォームです。いずれもドーサル・セパル及びペタルは赤色の斑点に覆われ、またペタルの先端部は細毛となっています。そこで今回グリーンフォームに関する情報についてネットで調べたのですが該当する画像は見当たりません。ネットに見られるラテラル・セパルのベース色は、淡黄色から黄味の強い萌黄色まであり、斑点についてもそのサイズ、形、位置も様々で、果たして同種かと疑うサイト画像もあります。当サイトの 一般フォームとグリーンフォームとの詳細な画像比較は画像下の青色種名のクリックで見られます。このグリーンフォームは2016年末の入荷株ですが、希少性の高いフォームと思われることと、炭化コルク取付で5年以上植替えの無かった株もあり、花後には杉板に植替える予定です。 |
 |
 |
| Bulbophyllum weberi Common form Mindanao | Bulbophyllum weberi Green form Mindanao | Bulbophyllum weberi Mindanao |
現在開花中のBulbophyllum inunctumとBulbophyllum glebulosum
現在(11日)Bulb. inunctum マレーシア・フォームとBulb. glebulosumにそれぞれ7輪と4輪が1株に同時開花しています。当サイトにおいては、これらの種で1株(凡そ10葉/株)当たりの同時開花数としては最多となります。Bulb. inunctumの花サイズは13㎝ x 5cmと大きいため、これが7輪纏まって開花すると可なりの迫力となります。下画像の左と中央は株全体と花部分を拡大しての撮影です。本種は花色の異なるフィリピン・フォームもあり、こちらは1株当たりのこれまでの最多同時開花数は6輪です。それぞれの花姿の詳細は当該バルボフィラム・ページに掲載しています。一方、右画像のBulb. glebulosumはフィリピン固有種で、昨年10月の本ページに取り上げました。これまで3回に分け、合わせて20株以上を現地ラン園に発注したものの、入荷株は殆どがミスラベル種で本種は僅か1株のみでした。また昨年と今年の猛暑を経ての今回の開花で、情報源となるサンプルの地域差に依るものかも知れませんが、IOSPEの本種情報(低―中温タイプと花サイズ2㎝)とは大きく異なることが栽培を通して分かりました。
 |
 |
 |
| Bulbophyllum inunctum (Malaysian form) Borneo | Bulbophyllum glebulosum Luzon | |
Paphiopedilum sanderianum
螺旋状に長く下垂したペタルが特徴のPaph. sanderianumを当サイトでは現在50株以上栽培しています。本種の一般種のペタル長は60㎝までとされますが、当サイトでは1mを超え、またその長さの継承性を確認した株を7株所有しています。殆どの趣味家にとって1m超えの本種の開花姿を直接目にすることは、その稀少性から難しいようです。下画像は現在開花中の本種で、ペタル長が1mに達した時点で撮影(12月8日)しました。 |
 |
 |
| Paphiopedilum sanderiannum Petal length: >1m Borneo | ||
10年ほど前にOrchidInnの販売サイトで、1m越えの本種の価格が円換算で150万円程であったことには驚きましたが、現在のマーケット価格は不明です。一般趣味家から見て、観賞植物一株にそれほどのお金を使うのは狂気の沙汰と思われるかも知れません。しかし稀少な花フォーム(Paph. sanderianaの場合はペタル長)が一過性ではなく、毎回の開花にその特徴の継承性が保証された株であれば、こうした価格であっても入手を希望する人もいるようで、その背景には観賞するだけでなく、実生化あるいはメリクロン培養を行い、将来それらを販売するビジネスへの目論見が考えられます。振り返って当サイトでもその当時、胡蝶蘭Phal.appendiculata albaやmicholitzii albaの野生栽培株を1株25万円で購入したことがあります。現在当サイトで1株の販売価格を数十万円とする種はTrichoglottis atropurpurea alba (flava), Bulb. maxillare alba, Den. olivaceum flava, Den. cymboglossum flava, Vanda. lamellata calayanaなど10種以上あり、こうした株は全て実生ではなく野生栽培株です。
現在開花中の6種
Bulb. rugosumは現在5株栽培していますが、今年の猛暑期間は中温室に移動しての栽培となり10月末に高温室に戻しました。その効果もあってか現在それぞれの株に、例年にない複数の新芽の同時発生が見られます。Den. fitrianumは2018年OrchideenJournal発表の4年も前に入手したもので、2018年以降はストックが無い状況でした。そうした中、下画像の株が今年6月にDen. atjehenseの植付け株の中に混在していたことが分かり、改めて株分けしたものです。6月の花と今月の花を比較すると、セパル・ペタルの赤みのある青紫色が広く濃くなっています。おそらく株が充実すればさらにこの色がセパル・ペタル全体を覆うと思います。本種の生息地は南スマトラ島、一方Den. atjehenseは北部スマトラ島とされます。なぜかなり離れた生息地のこれらが同じロット内に混在していたかは不明です。また本種は国内外ともネットでのマーケット情報は見られません。 |
 |
 |
| Bulbophyllum rugosum Sumatra | Bulbophyllum othonis Palawan | Bulbophyllum irianae NG |
 |
 |
 |
| Dendrobium fitrianum Sumatra | Dendrobium atjehense Sumatra | Dendrobium annae Sumatra |
Den. fitrianumについては、これまで中温タイプであるDen. atjehenseと同じ栽培環境であったこと、また中温室にて6月の植替え後に新芽の発生が見られること等からは本種の生息域は標高800mから1,000mと思われます。
Dendrobium rhombeumの高芽
下画像に示すデンドロビウムは今年2月、それまでの炭化コルクからチークバスケットに植替をしたDen. rhombeumの現在の姿です。その植替えの際、それぞれの株に発生していた高芽を外し、それらを元株の根元に寄せ植えしました。本種は例年1-2月頃 に、落葉した疑似バルブから複数の花茎が出て、多数の花を付けます。植替えから現在まで10か月が経過しましたが、今回取り上げたのは9月頃から高芽が出始め、下画像に見られるように現在では35本ほどの、高芽だらけの異様な光景となっているためです。デンドロビウムの高芽は主に根の弱体化や損傷に起因して発生するものですが、下段画像3株の根元の様子からは、2月の植替え時の高芽や植替え後の新芽に異常は見られません。しかしこのような様態では例年の開花期に向けての花茎の発生は期待できないと思います。夏からこの時期に至る間のこうした要因は、今年の猛暑で温室内の夜間平均温度が30℃以上となる環境が2か月間も続いたために生体機能が変化し、落葉している疑似バルブの節々では、1月の開花期に向かって花芽を出すべきところを、高芽寄りに代わってしまったのではないかと推測しています。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Dendrobium rhombeum Palawan (12月2日撮影) | ||
来月には上段画像にある凡そ35本の高芽を全て外し、それぞれを別の中型のバスケットに7-8本程を1株として寄せ植えする予定です。来年も今年と同様な猛暑が続くようであれば、夏期には夜間の栽培環境を30℃以下にする対応が必要かもしれません。
Bulbophyllum penduliscapum
大型のBulb. penduliscapumが新たに当サイトのバルボフィラム・インデックスに加わりました。本種はボルネオ島、マレー半島、スマトラ島およびフィリピンの生息種とされます。IOSPEでは本種を "quite spectacular" 非常に壮観、と形容するほどで、葉長は50㎝前後、また50㎝近い下垂する花序に200輪ほどの花を付ける迫力のあるバルボフィラムです。下画像は2018年ミンダナオ島から入荷した株で、左及び中央の画像は知人から提供(撮影は2022年11月)されたものです。右画像は左の成長株で、現在同人より株分けのため受託しており、昨日(11月30日)当サイトにて撮影しました。葉数が5枚ほど増えていることが分かります。右株が撮影倍率により左株と比べ小型に見えますが、葉長が50㎝程であることに変わりなく、左右の葉の先端間の横幅はNS(自然体サイズ)で1mを超える大きな株です。開花後には株分けを行います。本種の詳細は画像下の青色種名のクリックで見ることができます。 |
 |
 |
| Bulbophyllum penduliscapum Mindanao Bukidnon | ||