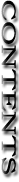栽培、海外ラン園視察などに関する月々の出来事を掲載します。内容は随時校正することがあるため毎回の更新を願います。 2018年度
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
10月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
| Plurothallis tarantula | ||
Bulbophyllum gracillimum f. flava
現在Bulb. gracillimumのflavaフォームが開花中です。このフォームはこれまで扱った200株(1株3バルブ換算)以上の中から出現した1株です。下写真上段左は今月植え替えをしたBulb. gracillimumの一部で右はflavaフォームの花です。下段左は一般フォーム、右は上段右の花を拡大したものです。 |
 |
 |
 |
| Bulb. gracillimum common form | Bulb. gracillimum flava form |
Bulbophyllum fascinator corazonae
タイ、マレーシア、スマトラ、ボルネオと広範囲に分布するBulb. fascinatorのフィリピンフォームであるBulb. fascinator corazonaeは、ミンダナオ島標高1,000mに生息します。付属名のcorazonaeはPurificacion Orchidのオーナーで、現Philippine Orchid Scciety (POS) 会長名に由来し、当サイトが在庫する株は全て当人から直接入手したものです。Bulb. fascinatorは生息地によって様々な色のフォームがあり、corazonaeフォームは下写真中央に示す黄緑のベース色に、えんじ色の斑点があり、しばしば黒に近い色も見られます。開花は秋から春が多く、当サイトの株は、左写真に見られるように、ラテラルセパル中央から先端部が緩やかにカールしながら紐状に長く伸び、ドーサルセパルからラテラスセパルそれぞれの端間のNSサイズは25㎝を超える大きな花です。右写真は今回植え替えを行った株の一部で、株の伸びしろ分を大きく取り、35㎝長のコルクに、根の乾燥を避けるため厚くミズゴケを敷き取り付けたもので、写真はそれぞれ葉付7バルブ程の株です。本種は下垂する花形状とそのサイズから、ベンチ置きのポット植えはできません。またフィリピン生息種は標高1,000mのため中温タイプとなります。高温でも栽培は可能ですが、開花を得るには中温環境が適しています。 |
 |
 |
| Bulb. fascinator corazonae | ||
バルブ間のRhizomeの長いBulbophyllum. virescensの新芽発生期
Bulb. virescensやBulb. binnendijkiiなどRhizome(バルブとバルブを結ぶ根茎)の長い種は、バスケット、トレーあるいはヘゴ板などいずれに植え付けても、2年もすればリゾームが伸び、新しいバルブはやがて植え付け材から飛び出してしまいます。そのまま放置すれば新バルブの根は空中に伸びたままとなり、余程の高湿度環境でもない限り成長は止まってしまいます。当サイトでは一部をバスケットに植えているものの、多くは60㎝程の長い炭化コルクに取り付け、新たなリゾームの伸びしろ分をなるべく広くとり、それでもやがてはみ出す時期が来れば、株分けして新たな植え付けを行うことにしています。Bulb. virescensはBulb. binnendijkiiとシノニムの関係とされていますが、標高800m程に生息することから当サイトでは高温室にての栽培となっています。一方、Bulb. binnendijkiiは標高1,000m以上の生息のため中温室となります。これらの新芽発生は春と、猛暑が去って温室内の気温が日中30℃以下、夜間20℃前後になる秋に盛んになります。下写真左はボルネオ島とマレー半島からのBulb. virescensで、中央および右はそれらに発生した新芽を28日に撮影したものです。ほとんどのバルブ基に新芽が見られます。しかし、こうした芽が成長し葉が開くまでの栽培は中々難しく、今年から植え付けは、これまで以上にコルク上のミズゴケを厚く敷き、決して乾燥させないようにしています。経験では、根周りの乾燥状態が繰り返されると、特に葉が開く前のバルブが未発達な新芽は縮み枯れ落ちることが多く、数ヶ月間は24時間常に根周りを湿らせた状態にすることが必要です。このため乾燥気味な環境ではこうしたコルク付けは適さず、景色は良くないものの、根を常に湿らせることが容易なトレーやバスケットにミズゴケを厚めに敷き、その上に植えつける栽培が有効です。
 |
 |
 |
| Bulb. virescens | ||
現在開花中のバルボフィラム4点
多数のバルボフィラムの開花期を迎え、当サイトでは種名不詳種が多いこともあり、これらの中にも入荷後始めて花茎を付けた株も数株に見られ、これからの2-3ヶ月が楽しみです。下写真は現在開花中のバルボフィラム4点です。上段左のBulb. pardalotumはBulb. ocellatumとよく間違えるのですが、リップ先端が扁平で丸みがある一方、Bulb. ocellatumは細く尖っています。標高1,200mの生息種です。写真右のBulb. nasseriはラテラルセパルの長さが5.5㎝ですが、ごく稀に8㎝程の長さの株が見られます。こちらは低地生息種です。下段左はタイ、マレーシアに分布するBulb. anandareiです。写真の花は一般種のラテラルセパルの長さに比べて短く、反面その幅は一般種と同じかやや広いため、丸みがあり可愛らしさを感じさせる形状で、orchidspecies.comではAnother Cloneとして画像を掲載しています。この株はマレーシアキャメロンハイランドで入手したものです。生息域は標高1,000mで中温タイプとなります。右はBulb. plumatum yellowです。一般フォームは紫色で、当サイトではこの一般フォームをシノニムの関係であるBulb. jacobsoniiとの種名で扱っています。よって写真のyellowフォームはBulb. jacobsonii fma (あるいはvar.) flavaとも呼ばれています。フォーム (fma) か変種 (var) かは本種が一般フォームの中に混ざって生息しているか、それらとは異なる地域に生息しているのかで別れますが、現在はfmaが主流のようです。標高は1,000-1,500mとされ、こちらも中温環境が適します。こうした標高1,000mから1,500mの中温種の多くは高温環境でも栽培が可能ですが、適温である中温での栽培と比べて、現状維持までか、株は伸長するものの開花が余り見られません。国内では、北陸、中部山間部、福島以北の、東海関東地域と比べ高温域で5℃程年間平均気温が低い環境であれば、高温タイプ(18℃-34℃)と同居しても成長や開花に問題は見られません。
 |
 |
| Bulb. pardalotum Luzon | Bulb. nasseri Leyte |
 |
 |
| Bulb. annandalei Malaysia | Bulb. plumatum f. flava Malaysia |
現在開花中のデンドロビウム4点
気温が下がり一日の昼夜の温度差が大きくなると各種で開花が始まります。現在浜松温室にて開花中のデンドロビウム4種を撮影しました。上段のDen. igneo-niveumは晩秋から春にかけて開花が見られます。写真は7輪の開花です。右は1昨年入手のパプアニューギニア生息のDen. vexillariusでセパルペタルは白色ですが、青色も8株程栽培しています。下段左のDen. dianaeはグリーン系、イエロー系、赤と黄色のツートンカラー系の3フォームが見られますが写真はグリーン系です。2010年登録の比較的新しい種です。また右はフィリピンミンダナオ島のDen. boosiiで、現在が開花最盛期で無数の花が開花中です。写真はその一部です。こちらも2011年登録の新種です。 |
 |
| Den. igneo-neveum Sumatra | Den. vexillarious white PNG |
 |
 |
| Den. dianae Kalimantan Borneo | Den. boosii Mindanao |
Dimorphaorchis lowiiとVanda floresensis cluster
下写真左は今年5月に入荷したDmrphr. lowiiの順化終了後の現在の画像です。多くの新根がバスケット内に出ており、一部バスケットの下に根が伸び出した株は湿度対策で不織布を巻いています。現在8株あり、一枚の葉長は50㎝以上です。ちなみに属名のDmrphrはDimorphaorchisの公式の略語です。一方、右は2016年入荷のVanda florescensisです。入荷時は伸長50㎝程の2本の茎からなる株でしたが3年間で1m近くまで伸長し、現在ではすでに30㎝-50㎝となった4つの新芽と、合わせて6茎のCluster株になりました。こちらは展示用として栽培しています。 |
 |
| Dmrphr. lowii | Vanda floresensis cluster |
マレーシアおよびインドネシアに生息する高価なVanda
フィリピンを除くマレーシアおよびインドネシア生息のVandaの中で、世界のマーケットにおいて比較的高額な種を下写真に取り上げてみました。写真は当サイトにおけるそれらの栽培風景で全て開花サイズの野生栽培株です。Vanda lombokensisiは15株程を、Vanda floresensisは6株、Vanda devoogtiiは5株、Vanda deareiは6株、またVanda foetidaは2株それぞれ現在在庫中です。これらVandaはNTOrchidを除き、国内ラン園を始めシンガポールAsiatic Greenでも現在ネットでのマーケット情報が見られません。Vanda foetidaは米、ヨーロッパ向けの2019年度価格でUS$70前後が見られ、上記他種(US$100以上))と比べ若干安価なようですが、下段右写真後方の株は1m超えの大株で、このサイスはかなり高額になるかと思います。当温室では上段中央写真に見られるように、幾つかの株に白い布が巻かれています。これは農業用不織布で、同居するVanda以外のランに合わせた温室環境ではベアールート栽培のVandaの根にはやや乾燥気味となるため、通気性や透水性を保ちつつ根周りの湿度を幾分長く保持する目的の処置です。また木製バスケットとしている理由は、根が木肌に良く活着するためで株はクリプトモスで抑えています。
Vanda lombokensisについては、上段左写真のコルク付けだけでなく、バスケット植えも半々で行っています。これまでフィリピン種以外のVandaの多くは、スリット入りプラスチック鉢に大粒バークで植え付けていましたが、気相や通気性が少ないためか当温室では良い結果が見られず、今年夏季からの植え替えではコルクやバスケットに替え、さらに根の乾燥を嫌う種には根周りに不織布を巻くことにしました。
 |
 |
 |
| Vanda lombokensis (Indnesia Lombok Isd.) | Vanda floresensis (Indonesia Flores Isd.) | Vanda helvola f. flava (Java. Sumatra. Borneo) |
 |
 |
 |
| Vanda devoogtii (Indonesia Sulawesi) | Vanda dearei (Borneo) | Vanda foetida (Indonesia Sumatra) |
Dendrobium sp (endertii aff.)のflavaフォーム
今度は歳月記2月に取り上げたスラウェシ島からのDen. spで、Den. endertiiに似たロット株にリップの褐色斑点の無い無地(薄い緑色)のflavaフォームの花が開花しました。昨年12月と今年1月に両ロット合わせて40株ほどを入荷した中の1株です。下写真左は一般フォームで、右が今回のflavaフォームとなります。 |
 |
| Den. sp (endertii aff.) Common form | Den. sp (endertii aff.) flava form |
Bulbophyllum inunctum、Bulbophyllum membraniforiumとBulbophyllum maculosum (sanguineomaculatum)
Bulb, inunctumが現在開花中です。本種は主にボルネオ島とマレー半島生息とされており、フィリピンにも生息するものの、orchidspecies.comには記載されていません。これはフィリピンでの発見が近年(W. Suarez氏の画像記録は2007年)であったためと思います。当サイトでは昨年フィリピンからBulb. glebulosumとの株を20株程入荷しましたが、これが全てミスラベルでBulb. inunctumでした。同じAurora州の生息のため取り扱いを誤ったと思われます。バルボフィラムとしては花サイズが12㎝と大きく、またマレーシア種は、セパルペタルのベースが淡いピンク色にベリー色のラインのあるフォームに対し、フィリピン種は下写真のようにベースが黄色で赤茶色のラインやドットが入り、それぞれの色合いは、かなり異なります。フィリピン種はバルボフィラムの中ではその色とサイズから、よく目立つ存在です。生息域は標高500mで高温タイプです。orchidspecies.comのシノニム項によると、4年前(2015年)にBulb. inunctumはBulb. membraniforiumの亜種に位置付けされたようです。そこで3週間ほど前に開花していたBulb. membraniforiumも下段左に示しました。ペタルとラテラルセパルの形状がBulb. inunctumとはかなり異なりますがリップはよく似ています。しかし上下段左が亜種の関係とするのであれば、歳月記4月末尾に取り上げたDen. deleoniとDen. annemariaeの、両者の違いを見分けることが困難な程の形状差にも拘わらず別種とした判断には甚だ疑問で、 その程度の差であっても別種とすることを是とするのであれば、むしろ下写真左の上下は亜種の関係ではなく別種の方が分かり易いと思えるのですが。こうした似た者同士の分類には人為分類ではなく生体分子分類法が必要と感じます。
一方、Bulb. membraniforiumで画像をネット検索すると、Bulb. maculosumを含めこれら3種がBulb. membraniforium名でごちゃ混ぜ状態で、あまりにひどいのでBulb. maculosum(本種は歳月記7月末尾に記載)も下段右に掲載しました。バルブの太さ形状はBulb. membraniforium >Bulb. inunctum > Bulb. maculosumとなります。花サイズは下写真からは分かりませんが、Bulb. inunctumは12㎝、他は3-4㎝程とされ、圧倒的にBulb. inunctumが大きいことがorchidspecies.comの記載となっています。これはペタルが、下写真上段に見られるように後ろに反った状態ではなく、開花後2-3日以内の反り始める前の左右に一直線に開いた状態時のペタルスパンの長さを表したものです。このような開花から日が経つとペタルが後ろに反る性質はDen. tobaenseやBulb. nitidumも同じです。当サイトでは下写真3種を今年の東京ドームやサンシャインで出品し、4バルブ1,500円から、35㎝炭化コルク付けの10バルブほどの株は3,000円で販売しました。
 |
 |
| Bulb. inunctum | |
 |
 |
| Bulb. membraniforium | Bulb. maculosum (sanguineomaculatum) |
Aerides lawrenciaeとAerides magnifica
現在、Aerides lawrenciaeとAerides magnificaが開花中です。Aeridesの中でAerides odorata、lawrenciae、quinquevulneraはそれぞれに変種やフォームが多く、フィリピンからの入荷にはミスラベルがしばしば見られます。最も簡単な識別はAerides odorataのリップは黄色、Aerides lawrenciaeは花サイズが4㎝以上と他と比べて2倍近い大きさであることです。下写真の左はAerides lawrenciaeで、中央はその花の拡大写真です。実はこれも2年前にAerides inflexaの注文で入荷した中のミスラベル株です。右はAerides magnificaで、これまでAerides odorata Calayanとか、Aerides quinquevulnera Calayanタイプとされていたもので、昨年夏ごろまでは入手難でしたが、当サイトでは本種の入手ルートがフィリピンに新たに確保出来たこともあり、比較的容易となりました。現在浜松温室では20株程を栽培しており、8株に蕾が見られます。現地ではほとんどがベアールートの吊るし栽培です。国内ではベアールートでは乾燥気味となるため、そうした環境では歳月記8月で取り上げたAerides leeanaで行っているコルク付けや、あるいはバスケットとクリプトモスなど、何らかの根周りの湿度を高める植え付けが有効です。バークとプラスチック鉢では気相や通気が不足がちになり、当サイトでは、これまで良い結果が得られていません。
 |
 |
 |
| Aerides lawrenciae | Aerides magnifica | |
Phalaenopsis modesta Sabah red
Phal. modestaの一般フォームはセパル・ペタルが白色ベースに淡い紫色の斑点をもつ小型の胡蝶蘭原種で、斑点模様は様々です。本種は葉下に開花することからヘゴやコルク付けで栽培されています。4年ほど前に、下写真左のセパルペタルのほぼ全体が赤紫(フクシャ)色の稀なフォームをもつ株が1株あり、これを自家交配し、1昨年フラスコ出しを行い現在は右写真のBS近くになっています。国内での本種の開花期は冬から春で、来春には初花が得られるのではと期待しています。花を確認次第、販売をする予定です。 |
 |
| Phal. modesta Sabah red | |
台風19号
台風19号の強風と豪雨により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。ここ浜松でも伊豆半島上陸の3-4日前までは、近くを通過する可能性も考えられ、また昨年の24号の記憶もあって温室業者に屋根のビスの点検や天窓のテープ留めなどを依頼し対応しました。お蔭で当温室は目立った損傷もなく無事に過ぎました。記録的強風とのことで、これまで以上に風で飛ばされる可能性のある屋外のものは全て、また多数のランの資材も屋外に置かれており、これらを一つ残らず固定したり納屋に取り込んだりと2日掛かりとなりました。台風が去った後には、今度はこれらを元の状態に戻す作業がやはり2日程続き、昨日15日にやっと終わり、今日明日からランの発送もできるようになりました。ランにとり最も好季節な10月が、温室には最も危険な月になるとは皮肉なことですが、今後とも自然の脅威にはできうる限り乗り越えていきたいと思います。現在開花中の原種
温度が30℃を切る気候になり多くの種で花芽が発生しています。下記写真は現在開花中の原種の一部を撮影したものです。 |
 |
 |
| Den. victoriae-reginae | Den. yeageri blue | Den. oreodoxa |
 |
 |
 |
| Den. endertii aff. | Den. sp | Bulb. dolichoblepharon |
 |
 |
 |
| Bulb. williamsii | Coel. longifolia | Coel, sp |
 |
 |
 |
| Phal. bellina wild | Phal. appendiculata | Phal. lindenii |
Bulbophyllum scaphioglossum
本種は2014年登録のニューギニア生息のバルボフィラムで、現在浜松温室にて開花中です。新種のためかorchidspecies.comには記載が無く、栽培方法についての情報はネットからは見当たりません。当サイトでは発見から2年後の2016年10月に入手し、同年の歳月記10月と11月に取り上げました。それ以来3年が経ち、栽培に関するデータもある程度得られたため今回再度本種を取り上げてみました。Bulb. scaphioglossumの形態情報はBulbophyllum scaphioglossum J.J.Verm. & Rysy, Orchidee 65 (2014) 142のサマリーで、また花画像はWikispeciesで見られます。入手時には標高情報がなく、その花や株形態がBulb. nitidumに似ていることから、低温室(15-25℃)にて栽培を1年ほど行い、新芽の発生と開花を確認しました。現在はその場所から中温(15-28℃)場所に移動し2年が経過します。その間に一回の植え替えを行い、現在は炭化コルク付けにしています。もっとも成長の良い支持材はヘゴ板で30㎝x10㎝と株に比べてやや大きめのサイズが最適です。
栽培で観察される印象からは標高1,200mの雲霧林(コケ林)生息のBulb. nitidumと同じか、やや低地と思われ、根は常に湿っている状態が必要です。雲霧林帯の生息種は一般的に低輝度環境とされますが、当温室での本種はLED直下の比較的高輝度な位置にある株の方が、葉やバルブに勢いを感じます。また低 - 中温タイプのバルボフィラムは高温に比べ成長芽の発生は遅く、多くても1年に2芽(2バルブ)程度であるものの古いバルブからの落葉も遅く数年もすれば大株になります。下写真は上段がBulb. scaphioglossumで7日の撮影です。右写真は株の一つで植え替えから2年間で2倍ほどのバルブ数になったものです。本種は大きなリップと、その中心に走る金色の太いラインが特徴です。下段は同じCodonosiphon節の左はBulb. speciosum、右はBulb. nitidum aff.です。生息地も同じニューギニアで本種の類似種として掲載しました。2016年の歳月記で指摘しましたが、orchidspecies.comでは現在もBulb. nitidumの生息域は1,200mのコケ林としながらも、温度マークは高温となっています。このhotマークは夜間温度が24-29℃の標高0-1,000mと定義されており誤記と思われます(Climate of Papua New Guinea, J.R. McAlpine、etal.著にはPNGの標高1,200mの最低・最高年間平均温度は15℃-26℃)。Bulb. nitidumは中温室あるいは山上げなくして日本の夏は越せません。
ちなみに上記のBulb. nitidum aff.のaffはaffinityの略で生物学名用語の近縁(類似)種を意味します。ネットでは下段写真右の形状に似たBulb. nitidum画像も見られますが、サイズが11- 12㎝とされているのに対し、右写真の株はラテラルセパルの長さが8㎝以上あり、左右のセパルが後ろに反る前の開いた状態ではスパンが16㎝を超え一般種とはサイズが異なることからaffとしたものです。Bulb. scaphioglossumについてのマーケット情報は国内には見られず、海外ではNT OrchidでUS$60.00が見られます。当サイトでは2016年11月の記載と変わらず、およそその半額です。
 |
 |
 |
| Bulb. scaphioglossum | ||
 |
 |
| Bulb. speciosum | Bulb. nitidum aff. |
Dendrobium serratilabium Green
Den. serratilabiumはフィリピン固有種でルソン島からミンダナオ島の標高500m - 1,200mに幅広く分布しています。その名Serrateが示すようにノコギリ状のリップ外縁形状が特徴です。昨年12月から発注をしてきましたが、3度目でようやく本物を得ました。本種の疑似バルブ形状はDen. victoriae-reginaeと酷似しており発注初回と2回目の入荷株は全てDen. victoriae-reginaeでした。しばしばDen. serratilabiumにはDen. victoriae-reginaeがミスラベルで混在するようです。バルブ形状からは同定が困難です。1昨年在庫が無くなったための新入荷ですが、当サイトでの本種の最初の入荷は2009年で、今年5月の入荷は10年ぶりとなります。| 本種は基部が細く、次第に太くなる40㎝程の疑似バルブをもち、またそのバルブの途中からから発生する新芽のバルブも同じ形状で成長し下垂することから、ヘゴ板等の垂直板あるいはバスケットへの植付けが必要となります。こうしたバルブ形状は同じCalcarifera節のDen. boosii、Den.. chameleon、Den. yeageriなどと共通しており、当サイトでは右写真に示すように炭化コルク付けとしています。 下写真は上下段が同じ株で、3つのフォームを示しています。本種の一般フォームは左に示すセパル・ペタルが薄黄のペース色にそれぞれ5 - 6本の赤いラインが見られます。このラインは花によって濃淡があり、セパル・ペタル全てに明瞭に、あるいは中央写真に見られる、一部に薄く入るものなど多様です。こうしたラインの色合いを反映しているかのように、それぞれの下段画像からは蕾の色から、開花時の凡そのフォームが推測できます。これまでの花の共通点は、中央写真の下段に見られるようにドーサルセパルの背面には赤味が見られることでした。 ところが今月、10年ぶりに入荷した株の一つにセパルペタルおよびリップが薄緑色一色で、全面また背面にも赤ラインのないalbaフォームのような花が開花しました。それが下段右の花です。中央の緑味のある株も右と同じロットです。一方、当初高温室での栽培でしたが今期の猛暑に今一つ元気が無かったため中温室に移動してからの着花であることから、緑味の強い今回のロットはこれまでの一般フォームと異なり、やや高地生息の可能性を感じます。 一般種と花のカラーフォームが異なる例は、当サイトのDen. crabro、今年8月歳月記のDen. cymboglossum、また9月歳月記で取り上げたDen. dianae、など、デンドロビウムにしばしば出現しています。それらに共通する特徴は赤成分が抜け、緑味が増すもので、これらをこれまでしばしばalbaあるいはflavaフォーム様態として取り扱われていました。しかし、厳密にはalbaあるいはalbescensは白色、flavaは黄色、aureaは金色を意味するラテン語で、右写真に見られるような緑色を指す言葉ではありません。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Den. serratilabium | ||
この背景として、ランの白色変異の花フォームにはしばしば緑色が混在することがあり、その緑色の割合が多い場合でもalbaとしたり、一方で、開花時は緑色気味であるものが、やがて薄黄色く変化する種があることから、緑色でもflavaとしていることがあります。本種は緑色が長く続きますがやがて薄黄色になることから一般種との差別化を表記する既存の通称種名としてはflavaとなると思われます。
10月のラン
来週7日からは、ようやく猛暑日が去り、 昼間25℃、夜間18℃前後の気温になる予報です。気温が低下し温室の換気扇の稼働率が下がり、窓も占めている時間が長くなると、温室内は一気に湿度が上がります。夕方に散水した葉上の水滴の一部が、翌早朝まで残るのはこの時期で、青々として張りのあるランが見られます。また昼夜の温度差が10℃近くになると、多くのランにとって最も成長が活発になり、春先とともに植え替えの好機でもあります。1-3月に開花の多い胡蝶蘭Phalaenopsis節のPhal. schilleriana原種などにとっては、これからの1-2ヶ月間の施肥等のケアーが有効となります。多くの趣味家にとっては、今年の酷暑を乗り越えた種もあれば、ダメージを受けた種もそれなりにあったのではと思います。当サイトの夏は低-中温室が避難所となり、吊るす隙間もないほどの状態になりました。これからそれらを元の場所に戻し、また植え替えは年中しているものの、特に希少種に対しては新しい植え込み材の交換を優先的に進めているところです。
今年の酷暑で高温タイプ用の温室内は昼間40℃近く、また夜間も30℃前後となる日が続き、多くの種がヘタリ気味でしたが、この中で我関せず状態の種の一つがDen. miyasakiiで、これほどの夏を経ても、まさに草むら状態です。本種は地生および岩生とされ、当サイトではバーク、赤玉土、麦飯石のミックスによるスリット入りプラスチック深鉢での栽培です。来週は四方に伸びた茎を少し整える予定です。今年の冬期から早春にかけては相当数の開花が見られるのではと期待しています。右写真が4日撮影のDen. miyasakiiです。
 |
 |
| Den. miyasakii | |
Dendrobium yeageri
Den. yeateriはフィリピンルソン島標高1,000m - 2,000mに生息する中温タイプのデンドロビウムです。ブルーの花で知られたミンダナオ島のDen. victoriae-reginaeと隣り合わせの栽培ができます。一般フォームとして本種のセパル・ペタルおよびリップはやや青味あるいは赤味のある紫色ですが、昨年リップが青色の花が開花し、歳月記2018年4月に掲載しました。その後この株は青色が再現することを確認し、数株を趣味家に分譲しました。今度は更に別株でセパル・ペタルの青味がほぼ消えた白い花が出現しました。下写真左は当サイトの一般フォーム、中央が昨年の青リップのタイプ、そして右が今回の花です。本種は赤や青の濃度が株毎に異なる特性があるようで、この違いは果たして株固有であるのか、温度等の環境に依存しているものかは、現時点で不明です。しかし同じ環境(隣同士)でも濃度の差が株によって異なる様態が見られることから、機会があれば1年毎に中温と低温環境に交互に移して花フォームを観察することや、実生化して親の色フォームが継承されるか調べてみたいとも思っています。
 |
 |
 |
| Den. yeageri | ||
Bulbophyllum makoyanum
Cirrhopetalum節のBulb. makoyanumはボルネオ島、マレー半島とフィリピンの生息種とされています。一方、本種名の花画像をネットで検索すると、花形状に纏まりが無く、Bulb. lepidumや Bulb. cumingiiのようにセパルが幅広で短い形状から、それに比べBulb. serratotruncatumやBulb. brevibrachiatumのセパルがやや長く幅細なものまで、明らかに異種と思われるにも拘わらずBulb. makoyanumと名付けられた状態です。その中でフィリピン生息種は、放射線状に伸びた4㎝ x 2mmの極細のラテラルセパルが特徴です。下写真は浜松にて現在開花中(左)の花と、円形に広がったラテラルセパル間のスパンが13㎝の花(右)です。これほど花画像(形状)が曖昧であることと、当サイトではボルネオ島とマレー半島からは、下写真のフィリピン生息種と同形の花をこれまで確認していないこと、一方でフィリピンからのBulb. makoyanumは全て下写真と同じ花形状で、Palawanからミンダナオ島までの全土に分布していることから、このラテラルセパルの極細フォームを持つ種は、その種名は兎も角、フィリピン固有種ではないかと感じています。
 |
 |
| Bulb. makoyanum Philippines | |